| 対談・北田玲一郎の作家活動とその作品群 -p6- <前のページ:次のページ> |
||
『小説司法書士』……司法書士はノベルのヒーローたりうるか ━━ それでは次に、第三の活動領域の代表的作品ともいえる『小説司法書士』に話しを進めたいと思います。北田さんは、従来、小説のテーマとしてとりあげにくいといわれていた司法書士という職業を、小説として作品化され、1987年(昭和62年)に日本評論社より、『小説司法書士』という本を出されました。 この『小説司法書士』について、作家でもありまた弁護士でもある和久峻三さんは、1988年〔昭和63年〕6月18日の図書新聞の書評のなかで、「著者は、自らの体験をふまえ、ものの見事に司法書士の人間像を浮き彫りにしてくれている。」と書いておられます。 一方、北田さんは、この本の「あとがき」にもありますように、「司法書士とその業務をどう描くか、あるいは、いったい司法書士はノベルのヒーローたりうるのか、ということについては作家としての大きな悩みであった。」と書かれていますね。 この点については、和久峻三さんも書評のなかで、(司法書士という職業は)「苦労は人一倍多いのに華やかさに欠ける地味な職業のように思われがちで、なかなか小説の主人公にはなりにくい。とりわけ、エンターティメントともなれば、なおさらである。」と、同意見をお持ちのようです。 しかし、『小説司法書士』を読み進みますと、さきほどの書評にもありますように「ものの見事に」司法書士はノベルのヒーローたりえていますね。ここで、『小説司法書士』に収録されている作品群を紹介しますと、 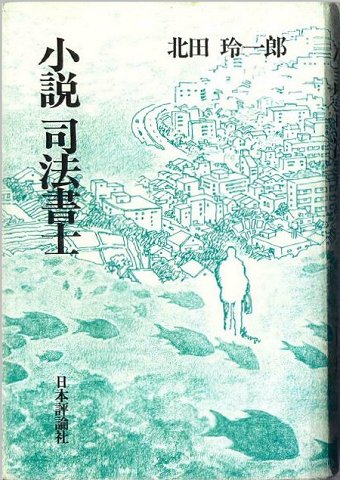 「秋雨」 「秋雨」「Oの肖像」 「トロール船の歌」 「引き裂かれた時」 「ふるさとのバラード」 「百日紅のある風景」 「河畔の風物詩」 「司法書士になった息子への長い手紙」 「落とし穴」 「合歓井先生見聞録」 「眠れる島の登記簿たち」 「愚かなる旅」 「新春猿蟹合戦」 「夜明け」 「砂漠の幻影」 「五月雨」 ← ですが、『小説司法書士』に序文を寄せられた江藤价泰教授は、研究者の立場から、これらを、第一に「司法書士の職務執行に伴う民事および刑事の責任の厳しさを直接のテーマとする」作品群、第二に「司法書士の現実の存在形態を多面から描いている」作品群、そして第三に「司法書士制度の歴史にかかわる」作品群というふうに三つに分類されています。 そして、「著者は、この司法書士にとっての根本問題――それは国民の権利にかかわる重大問題である――の解決を希求し、その実現のために司法書士はいかにあらねばならないかを、小説という形式をとって問題提起している、と考えられる。」とのべておられますね。 北田 僕にも司法書士はいかにあるべきか、ということはもちろん常に頭にあったんですが、とにかく、司法書士とその業務を小説化するのにどう描くかということでずいぶん悩んだわけです……司法書士制度研究第一人者の江藤先生からいただいた序文は、制度の分析にもなっていてありがたいですね。 このあと僕は、『月報司法書士』の207号(1987年〔平成元年〕2月号)から、「司法書士太平記」を連載執筆してるんですが、都合で未完になっている。作者としては自分の作品が眠ってるいうのは残念なことで……完になるところまで筆を進めたい思っとるんです。どこかで復刻してほしいですな。この企画のホームページでもいいですから…… ━━ 『小説司法書士』は、司法書士制度上のあるいは職務上の問題点を、多角的にそして深く抉っていて、読者にするどい問題提起をしていると思います。また、この本の表紙カヴァーの絵が、制度の姿を象徴しているのではないでしょうか……司法書士らしき一人の人物が鞄を持って後ろを向いて立っている、街の方向をみながら……司法書士の心象風景を描いているような気がします。 私が実務家として、『小説司法書士』を何回かくりかえして読み、作者がこの作品を通して何をいわんとしているかを、私なりにまとめてみますと、先ず、 ①そもそも司法書士とはいったいなにものであるのか、という最もわれわれ司法書士にとっての原初的なテーマが問われているように思います。そしてそのような問題意識に立って、②核心をついた社会批評あるいは人間批評がなされている。それから、③司法書士制度に内在する問題点のするどい剔抉がありまして、この制度の行く末がいかにあるべきかということを読者に問うていると思うんです。 さらに、④司法書士業務の「日常性」。北田さんは作品のなかで、好んで「日常性」という書葉を使われているように思いますが、この「日常性」をふみはずした司法書士の苦悩、あるいは、いつでもだれでも「日常性」ふみはずす可能性のある司法書士業務について、非常にリアルに描いてあると思います。さいごに、⑤司法書士制度の歴史とそこに登場した人物の生きざまや哀歓など、その見事な描写がありますね。 ここでは紙幅の都合から、「司法書士になった息子への長い手紙」と「夜明け」をおもな手がかりとして、司法書士とはいったいなにものなのかという問題と、司法書士制度史上に登場した人物像をとりあげてみたいのです。そこでまず、北田さんが司法書士とその業務を描かれるにあたって、作家としてどのような悩みがあったのかというところからお伺いしたいと思います。 北田 ずっと以前からいわれてるんですが、労働者文学、ことに、左翼系の文学では、現場を描くといいますか、毛沢東がいったような「下放」、労働の現場をリアルに描くということが民主主義文学のテーマだということがいわれてきたわけです。そういう労働組合系の作家、サークル作家の場合は、厳しい資本の管理下に置かれるておるところの労働現場というものを描くことによって、人間疎外とか階級闘争を描いて、政治プロパガンダ化してくる。 ですが、僕の立場では、同じ労働現場を描くといっても、司法書士の場合は、人間疎外とか、階級闘争とかいうのは、あまりないわけで、むしろ、自由業として主体性というか、実存を確立している。そうすると、それも当てはまらないわけですね。 いっぽうではエンターテイメントとしてのおもしろさということになってくると、弁護士なんかは常に法廷での攻撃と防禦というふうな、しばしば映画やテレビドラマで登場する形でノベルのヒーローたりうるんですけども、司法書士の場合は、「日常性」というものは閉鎖的な事務オンリーで、全くドラマチックでないわけであって、これもまた成り立たないような分野なんですね。 『月報司法書士』の編集部から連載の話があったときにずいぶんと困ったんですけども、それならば最後の分野として、自分の個人的な体験、そういったものを私小説風に書く。私小説風に書くということになってくると、また第二の問題が起こってきましてね。 だいたい、日本の私小説の風土というものは、日常生活というものを非常にリアルに、そして告白風に書くわけですよ。その場合、その主人公というものは、アウトサイダーでなかったらいかんのです。私小説の文学としてのかがやきとか栄光はそこにある。 社会からのはみ出し者、余計者でないことには、俗物や平凡なサラリーマンを書いたって純化された私小説にならないわけであって、秩序、組織から疎外された一人の自由人、隠者的で、同時に、反抗的なアウトサイダーの、常識的な社会モラルへの抵抗を書くのが日本の伝統的な私小説であって、太宰治、坂口安吾、田中英光の小説だってそうです。 しかも、自分が主人公で、自分の恥部を告白的に世間にさらすという私小説的演技がいる。司法書士というのは別の言葉でいえば、実存主義的な、この一瞬だけがすべてという刹那的な孤独な職業なんですね。だから、僕の司法書士生活というものを私小説的に書く場合に、どうしたらいいかというところでずいぶん筆が渋ってしまった。 しかし、とにかく、日常ぶつかっておるところの司法書士の労働現場といいますか、その労働現場を突きつめていくと、司法書士というのは、まさに孤独な、たった一人ですべての責任を引き受けねばならない、そういうところに座標軸を置けば、なにかやはり一つのノベルの形態になるんではなかろうか…… そういうところで、手探りで書き出したのが、まず「秋雨」なんです。だから「秋雨」を書いたところで多少の自信はついたんです。でも、「秋雨」では全くその日常を書いただけで、なんら一つのドラマチックな構成というのはとっていないわけです。 ━━ なにかの本のなかで北田さんは、司法書士あるいは司法書士業務を小説のテーマとしてとり上げるについては、思うように筆が進まず、「原稿用紙の上にフケを掻き落とす日々であった。」というようなことを書いておられましたが…… 北田 そのフケを、口をとがらして、フーッと吹く。(笑い)ところが「秋雨」を発表した後に問題が起こりましてね。本のなかでは書き直しましたが、初出稿では、冒頭の書き出しに「びっこの犬」がでてくる。それは、孤独な司法書士の心象風景としてでてくる。 ですが、「びっこの犬]というのは差別用語ということで過去に問題になってるんです。「びっこ」という言葉が。そうすると、当時、広報担当の副会長から電話がかかってきまして、これがもし差別用語ということで連合会が抗議を受けた場含、早速理事会を開かないかん。 作者はどう思うかという。僕としては、『新日本文学』に載ってる伊藤人誉の小説にびっこの猫のことが書いてるんです。『新日本文学』の場合は左翼文学ですから、被差別者がわに立つ文学ですからね。しかし、これは、作家がわの意識構造の問題であって、ふかく自己批判しています。 ━━ それから北田さんは、しばしば文章のなかで「蠱惑に満ちた」という言葉を使っておられますね。蠱惑というのはなかなか難しい口葉で、「人のこころを惹きつけて自制心を失わせる」というような意味のことだそうですが、「秋雨」以降これだけの作品を書き続けてこられたということは、やはり司法書士という職業が、蠱惑に満ちた、そしてユニークな職業であったからであろうと推察するんですが…… 北田 それは文字どおりそのとおりだと思いますよ、この司法書士という職業は。先ほどいいましたように、稀にみる孤独な職業ではありますが、自分ですべてを処理するというか、一種の賭けみたいな臨場感あふれる職業でしょう。僕の言葉でいえば、先ほども言いましたように自由業として実存を確立している。 だから、立会なんか僕の一声で大金が動きだすわけで、その一瞬一瞬というものにたいする緊張感といいますか、サスペンスというか、なにか自己の存在そのものを傾注するというところで、神経は摩耗するが、三日やったらやめられん職業じゃないですか。 ━━ いま、北田さんは業務そのものが蠱惑に満ちている、というふうにいっておられるのだろうと思うんですが、私はまた、常に向上を求めてたたかう制度であるという意味において、この制度自体も蠱惑に満ちていると思うんです。司法書士制度の歴史を学ぶと、まさに法改正の歴史ですからね。 北田 それは、そういうこともいえるかもしれませんね。いろいろ欠陥だらけですが、欠陥があるからこそ、また皆さん、たいへんプロボクサーの浪速のロッキーみたいに元気で、ファイトをわかして大声だしてやってるわけですから。 |
||
|
|
||
| 前のページ : 次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |
||
|
|