- p2 - 私の空襲体験 ― くたばれ飛行機/乞食(ビート)になるか/文化遺産としての除籍簿を残せ ◆ <p1> 生ける法を限りなく民衆に近づけるために/井上孝次郎の西部魂/『回顧と展望』編集後記 『司法書士公論』創刊宣言 痛切な主張の拡声機に/『司法書士公論』創刊号編集後記 <p3> 司法書士業余作家からの文学的メッセージ |
||
|
私の空襲体験 ― くたばれ飛行機 北田玲一郎 国民学校初等科のころ、「軍艦合せ」というゲームがはやった。戦艦、巡洋艦、駆逐艦、戦車、地雷、工兵、歩兵・・・・・・いろんなカードがあって、戦艦は巡洋艦に勝ち、潜水艦は戦艦に勝つが、駆逐艦に負けるというぐあいに、カードの奪いあいをするのだ。 そのなかの飛行機というカードは、これはオールマイティにひとしく、ほとんどのカードに勝つのであった。ただひとつ、高射砲に負けるのだけれど、そのくせ高射砲は飛行機に勝つだけの存在で、他のすべてに負けるのである。 こうして飛行機と高射砲は、僕ら少年のあいだにたいへんな人気があり、まったくこの二枚のカードの虚々実々のかけひきこそが、ゲームの戦局を左右し、まるで巨神戦なみの力のいれようだったのだ。おもうに、僕らのあの時代の飛行機熱は、この「軍艦合せ」からはじまったといえる。 わが零戦から飛燕、月光、彗星、そして、わけても鬼畜米国の双胴戦闘機P38、白銀色にそりかえった高速戦闘機P51、黒いハゲタカみたいなグラマン艦載機、長距離重爆B29・・・・・・その他、彼我の機種は、ことごとく暗記し、路上、壁、塀、いたるところただちにデッサンしうるぐらいであった。 このように飛行機が少年たちにぜったいに人気があったことは、ひるがえって、あの太平洋戦争の歴史は、なによりも飛行機で開始され、飛行機で終結した大戦であったという以外にないのではなかろうか?真珠湾奇襲から始まって、マレー沖海戦、パレンバン占領、ミッドウェー海戦、ガダルカナル、サイパン、硫黄島、沖縄、本土空襲、広島原爆投下にいたる戦史は、飛行機の快哉であり、反面、飛行機の悲惨であった。 「軍艦合せ」はだれがかんがえだしたのかしらないが、ゲーム(戦争)は、大空を支配したものが勝つということを、みごとに洞察していたのである。そして、いまや大空の完璧な支配への大国の意志は、アポロ11号やルナ15号に結晶し、月の獲得にまで発展したのだ。 それゆえ、僕の戦争体験とは、一言にしていえば、ぶざまで、哀れで、無抵抗で、歯ぎしりするほど悲劇的で、同時に滑稽な飛行機体験そのものといって過言ではない。「軍艦遊び」の初等科から、旧制中学生になると、僕たちの頭を占領したのは、少年航空兵、予科練という空への平均的イメージにほかならなかった。デッサンした飛行機の実物に搭乗せねばならない。 およそいつの時代でも、若い世代のイメージは、画一的にその時代に支配されるのが趨勢というものであり、こんにち、全共闘の学生が、封鎖した校庭で、リーダーの呼笛にあわせ、米帝粉砕を、ヘルメットと角材にこめて突撃演習をやっているのとひとしく、僕らもまた、大東亜共栄圏を信じて、鬼畜米国打倒のために、校庭で、軍事教官の号令一下、鉄甲と木銃を歩兵操典にあわせ、藁人形に突撃したのである。 ところで、ナナツボタンは僕らのオールマイティであったのだが、ついに永遠に飛行機を手にいれて、大空をかけめぐることはなかった。それどころか高射砲にさえなれず、我物顔に飛びまわる敵機は、僕らにモグラの習性だけを教えた。壕穴の湿った粘土のかびくさい臭いには馴れたが、あの大空の澄みきった香ばしい匂いとはとうとう無縁だったのである。すこし兄貴の世代の予科練が、僕らにさえ土科練と蔑まれ、穴ボコ堀のモッコかつぎをしていたのに、どうして敗戦のとき十四歳の僕らに、栄光ある出番がまわってこようか――。 わが飛行機は空襲警報の鳴りひびくまえに、貴重なガソリソを使って逃げていく。敗戦まぎわになって石油がなくなると、ぜんぶ松林や藪のなかに隠匿してあった。空には敵機だけが飛びまわり、竹槍などをふりまわしても、トンボとりみたいなわけにはいくものか。 ちょうど、反代々木全学連の若者たちも、ホワイト・ハウス詣での飛行機に乗った佐藤の栄チャンに、空に向って吠え、角棒をふり、石を投げたが――しかし、僕らの体験からいえば、星を落しとろうとして竹竿をふりまわす男の話をおもいださないでもないのだ。 それに、あの軍艦合せでは、唯一の飛行機に勝つカードであった高射砲が、実戦では一度も敵機に命中したのをみたことがなく、それどころか、空中でスカ弾になって炸裂し、やがて絶対確実な地球の引力だけにしたがって落下してくるその鋼鉄の破片は、戦慄すべき鋭利な、ギラギラした天のマサカリのような兇器の役割を果した。 まるで、内ゲバの襲来である。敵機に発射されたはずの高射砲弾を、真に恐怖するのは、ぎゃくに僕らであるとは、なんたる皮肉――。そして、戦争が終ったその翌日から、僕らは、松林や竹藪に隠匿してある日本機を、ハンマーで叩き潰す作業にかりだされたのである。愚かなる転向の運命がそこにあった。 少年の日の夢を賭けた飛行機を、自らの手で破壊せねばならないとは。新宿闘争の学生が、大学を卒業し、生存の宿命から、こぎたない帝国主義資本にモーレツ社員とかおだてられて、数枚のつば臭い紙幣とひきかえに、青春の論理を埋没させる以上の転向であろうか・・・・・・。 こうして、朕の命令に、マッカーサーの命令がとってかわり、彼がダグラス輸送機で厚木空港にのりこんできたその日から、冷厳にも日本には一機の飛行機もなくなったのだった。おもうに、戦後二十数年のこんにちでも、わが国産の飛行機はいったい何機あるのであろうか?自衛隊と航空会祉に問いあわしてみてもいいのだ。 結論からいえぱ、大空=飛行機を支配しているものが、僕には地上の人民を支配するもっとも現代的な権力であるきがする。ただひとつ、破壊した機体のタイヤをゴム草覆にしてはき、窓の風防ガラスの破片を、連日の停電の夜のローソク代りに使用したのは、せめてもの無抵抗な転向反権力のがわの狡猜な生活の知恵というものであったろうか・・・・・・。 たしか、昭和二十年六月のある日だったと記憶する。午後、空襲警報とともに運動場の壕に避難した直後に、ゴーゴーという地鳴り状の音が壕壁をゆるがし、つづいてザザザアという大雨の音、あるいはバリバリバリという雹の無数に降りそそぐ音がかさなったとたん、中学校の校舎の屋根という屋根に、クリスマス・ツリーの燈のまたたきというのか、おびただしい燐の鬼火の大群というか油脂焼夷弾の陷が燃え、熔融して流れ、ひさしをしたたり落ちた。当時、学校には、中学二年の僕らと一年生しかいず、三年以上は工場動員にかりだされていた。 がらあきの校舎には、いれかわりに陸軍とS金属が入っていた。その眼もくらむばかりの火陷の花の開花をみたとたん、だれもが壕をとびだし、校舎に向って走りだした。瞬聞、隣りにいたTが、「いくな!油かぶって死ぬぞ!」と怒鳴った。どうやって、あの興奮の極限で、Tがそんな冷静な判断をくだしたのか、いまおもいだしても僕は畏敬の念にたえない。 たしかに、たちまち濃褐と真黒な煙、大きな真赤な先のとがった舌を吐きだす火焔につつまれた校舎に、ええかっこして消火作業にとびこんでいった連中は、煙にまかれたり、油をかぶったり、屋根からころがり落ちてくる六角の焼夷弾の筒にあたったりしで、火傷するものが続出した。 なにしろ、防空頭巾が火熱で乾いて紙のようにパッと燃えだし、紐を解くまに火傷してしまうのだ。「プール、プールへとびこめ!」Tの指図で、プールの水で全身ずぶぬれにしてから、Tと僕は校舎にとびこんだ。なにしろ、彼にも僕にも、多少は火の粉をかぶっておかないと、後ろめいた気持があったのだ。 二階の廊下には、大楠公崇拝の漢文の教師が仁王立ちになって、生徒の運んでくるバケツの水を窓にぶっかけている。廊下をものすごい煙が渦をまいてはしりぬける。窒息感、とおもった瞬問、火陷が矢の束となって天井を這いはしった。後ろめたさもくそもあるものか、Tと僕はうなりながら階段を転がり降り、遁走した。 運動場では、陸軍の兵隊とS金属の社員が必死で荷物を運びだしている。驚いたことには、兵隊がやっていることは、消火作業などではさらさらなく、米俵を気ちがいのように放りだしているのだった。社員は机の抽出しごと窓からぼんぼん投げる。たちまち運動場は、米俵と製図機械やらでいっぱいになった。 そして、このばあいでもTの頭脳のはたらきには舌をまいた。運動場にはものすごく上等のコンパス、鉛筆、定規、ノート、計算尺――当時の物資欠乏の中学生にとっては、かけがえのない垂涎ものの器具が散乱しているのだった。「・・・・・・パクレ、パクレ」とTがささやいた。いうよりはやく、彼はそれらをポケットにねじこんだ。 さらに感心したのは、その日の夜、まだ陷をあげたりしてくすぶりつづける焼跡の傍にへたりこんで、兵隊が運びだした米の炊出しの煙臭い握飯をほおばりながら、Tがワアワア泣きだしたことだった。学校が焼けてしまったといって泣いているのだ。その結果は、例の獅子奮迅の漢文教師から、ポケットにコンパスをつめこんだTは、忠君愛国愛校精神NO1の定評をかちえてしまったのである。 つづいて、同年六月、伊丹空港周辺(大阪府豊中市麻田、走井=現在螢ケ池)は、一トン爆弾と焼夷弾の混爆をうけた。爆撃は午前十時ごろからはじまった。すこし薄雲りの日で、なぜ僕はその日登校しなかったのか憶えていない。町内会のつくった松林のなかの横穴壕に避難していたが、飛行場の滑走路が狙われていることはあきらかで、爆弾の炸裂のたびに、壕壁、支柱がゆれ、土くれがひっきりなしに流砂のように落ちた。 ごうごうと轟きながら空をわたるB29の大編隊の爆音が、あとからあとから一時聞ぐらいつづいた。ふいに、はりつめた太い鋼鉄ロープが切断され、稔り、空中にまいあがっていくようなものすごい擦過音がした。つぎの瞬間、土砂がかぶさり、夢中でもがき、はねおきた。壕穴の男女、子供が泥亀みたいにもがいていた。 「直撃弾や!」はねおきただれかが叫んだ。壕をとびだして愕然とした。三十米ほど向うの泥田に、巨大な深い円い穴があいていた。穴――というより、大地が想像を絶する巨きな爪でえぐりとられ、穴の周りが赤土の土壊でうずたかくもりあがっていた。空は真黄色に焦げ、もはや嗅ぎなれたなんともいえないきな臭い小雨が降りだした。 熱い雨には黒焦げの紙片、布切れがまじってえんえんと舞い降りてくる。警報が解除され、在郷軍入や町内会の男たちが右往左往した。僕はその空襲で、はじめて人間のバラバラ屍体をみた。かんたんにのべる。頭、腕、胴、指、脚・・・・・ちぎれた断片はバラ色の肉の花弁という以外にない。ぼんやりみていたら、腹から腸のはみでた駄馬が、内臓をぶらさげたまま、どういうわけか倒れずにポクポク歩いていた。一面、黄褐の糞尿色の世界。 家が燃え、樹木が黒焦げになってそびえている風景を背に、その駄馬は歩くことだけが義務のように歩いて、どこかへいってしまった。市役所の人たちが木炭トラックに乗ってやってきて、屍骸のまとまりのない断片を、スコップですくっては荷台に放りあげた。人肉は、なぜあれほど臭いのか。乾パンの特配があった。ゲエゲエ嘔気がするのに、へんにいくらでも食べた。 それから、七月、八月がつづく。紀伊半島沖に米大艦隊がやってきて、くるわ、くるわ、真黒なズングリしたカラスみたいなグラマン、真白なカモメみたいなP51、艦載機が大群をなして、高いとこ飛んでるな、とおもうまもなく、いっせいに鳴き叫び交尾しながら急降下して、頭上すれすれに飛行場に襲いかかる。機銃掃射はミシンの針のように大地の割れ目を一直線に縫っていく。 後年、僕は、ヒッチコックの「鳥」という映画をみたが、こりゃ空襲映画だと思った。彼は、伊丹空港空襲の艦載機パイロットではなかったか?ヒッチコックに追われたモグラの群が、国道を北へ北へと煙色の顔に眼だけを光らせて列をつくって流れていった。南――大阪の方へ向っていくものは一人もなかった。 やがて、北摂の山脈の横穴掘りに動員されていた僕は、疎開の荷物運びでしこたま儲けていた馬力ひきのオッサンから、帰途、マッチ箱ほどの新型爆弾が広島に投下され、ずるむけに火傷して死ぬことをきいた。つづいて、ソ連が参戦した。夜、Tがきた。「暑いから爆弾池で泳ごや」艦載機が落していった木製のガソリン補助タソクの上部をくりぬいたボートも浮べてあるという。 それにTはばかにきれいなパンツをはいていて、指でさわると柔かく女物のようななよなよした感触だった。「これ、絹やぞ」と彼はいった。「どないしたんや?」ときくと、「アメリカの落下傘でつくったんや」といった。Tの家は焼夷弾で焼けたが、田舎の疎開先がなく壕舎住いをしていた。ある空襲の夜、邸の焼け跡に珍妙なものが降ってきた。どういうわけかしらないが、それは天女の羽衣のような落下傘だったのである。その上等の絹は、Tの家族のパンツに化けた。 「みてみい、この戦争負けたで。アメ公の落下傘みて、つくづくおもった。こんなええ布使うとる国に勝てるけえ」翌日の正午、戦争が終った。その日の夕暮は真夏の茜色に映えて美しかった。一機の飛行機も飛ばず、ふしぎな静寂が支配し、風景だけが生きていた。戦後がその日からはじまり、Tと僕は焼夷弾の鉄筒や壕の掩蓋の鉄板を売って、その金で闇市の大福餅をたらふく食い、下痢をした。 漢文教師が共産党に入党し、近所の戦死した航空隊の中尉の未亡人が、鳩の町で、ミネソタというバアをはじめた。だが、そんなことは、もう二十数年前の遠い想い出であるか?とはいえ、大空が大地を支配したあの時代、あのオールマイティの飛行機の恐怖的体験こそが、戦後の憲法をつくりだした母体であることはまちがいない。その証拠に憲法第九条には、「くたばれ、飛行機」と明記してあるのである。 それゆえ、このいくらかいてもそれ以上のなにかが洩れ落ちていくきがする小文で、真にのべたかったことは、ようやく二十数年前の僕の年齢に近ずいた僕の息子に、憲法がどうしてできたかを、その片鱗でもいいから語り残しておきたい誘惑にかられたからにほかならない。だれにでも父親には、なにかひとつ息子に遺産相続させるべきがらくたものがあるわけだ。この愚劣で哀れな遺産! (作家)  (『私の空襲体験』236頁/くたばれ飛行機/ ノーベル書房/1969年) ★写真をクリックで拡大→ 人間の発見Ⅳ 『道なき道』 4 怠惰と反逆 アウトローの五章 ①乞食(ビート)になるか 北田玲一郎 ビートの哲学 ビートの哲学――それは、労働を拒絶したことである。彼らは、死んでも、あるいは、たとえなぐり殺されても働くなどということは、絶対にしないということであろう。他人のために労働するなどということは、最低だとし、社会にさよならを告げたのだ。ある意味でいえば、彼らは意識的に労働を拒絶する以前に、働くことが本能的にきらいなのだ。 ビート乞食は、沖仲仕や土方や工場労働者、建設労働者に勝るとも劣らない、健康でたくましい若い肉体をもっているが、それゆえに、生来のなまけものということもできる。かつ、たしかに、生来的になまけもので、労働忌避の精神を一生もちつづけることのできるものだけが、ビートになりうるだろう。 なぜなら、人間は本来労働を愛するものであり、働くなといっても、自然に働いてしまうという性質をもっているからだ。原始時代の男たちは、石斧、弓矢を手に狩りに出て、妻子のために獣の肉をもちかえったし、それが唯一の自己の生存の証明であり、労働こそが人間としての存在価値にほかならなかった。 さらにまた、人間にあたえる最高の極刑が、無為――いかなる労働もなさせず、牢獄に入れることであるということは、つねにいわれるところだ。それは人間に、人間としての存在理由、つまり労働をあたえないことによる苛列な精神的苦痛を目的とする刑罰であったはずだ。いいかえれば、人間から労働を剥奪することは、死をあたえることを意味したからである。 人間が労働をやめるときは、通常、死ぬとき以外にないのだ。したがって、ナチス・ドイツの強制収容所の強制労働は、精神刑罰的にみて、いまだしの感をいなみえないのが、その残虐行為の一点の救いであろうか。その意味あいにおいて、アルベール・カミュが『シジフォスの神話( )』で展開した哲学は、なまやさしいものであるといえる。 シジフォスの無目的労働のアプシュルドなど、ビート乞食の労働拒絶のラディカリズムにひきくらべるなら、まことに小市民的であるといわざるをえないであろう。なぜなら、シジフォスには、永久に転落する岩を、汗水たらして永久に山の頂に運び上げるという永劫運送業者としての価値ある労働があったというべきである。 これをカミュのように、アプシェルドというなら、シジフォスの孫たる日本のダンプカーのジャリトラ運チャンの労働をなんと表現すべきであるか。ジャリトラ場から工事現場へ、工事現場からジャリトラ場へ……なんというアプシユルド! ある意味で、日本ビート乞食の労働拒絶の哲学は、実践的革命の具体的方法論を教示しているといえる。第一に、「働くな、といっても、愚かにも、えいえいと働き蟻のごとく働く」現代労働市民にたいして、「乞食倍増」のキャンペーンを自分の実践行動によって示すことで、人間革命の可能性を示唆している。 簡単にいえば、そのときになりさえすれば、働かなくとも乞食になって食っていくことができるのである。なんのためらうことがあろうか、おれをみてみろ、とビートはいう。働かなくても、「もらいもの」(ビート語)で、けっこう食って生きていけるではないか。 たしかに、ビート乞食の群れは、現代の都市賃金労働者の、賃金と物価上昇との永久的な悲惨なマラソンからくる日常的不安、焦燥の神経衰弱的精神状況にたいして、ひとつの有効な治療法をもっているだろう。安賃金で働くのをやめて、今日から乞食になりなさい。乞食は気楽で、人間的で、自分のスイング(ビート語)さえ考えていたらいいのであって、なんというすばらしい人生だ! 要するに、このキャッチ・フレーズは、内的決断、実存主義的にいえば、選択の問題でありつまり、人間革命の問題である。総理大臣、社長、部長、課長、工場長に相談する必要は、さらさらないのだ。きみは、ズダ袋と革靴さえ準備すればOKなのであり、ある日、忽然と、オフィス、あるいは、工場からいなくなるのだ。人間管理も就労規則も、クソクラエだ。 第二に、乞食主義は、マルクス・レーニン主義をけおとすだろう。コミュニズムは、資本主義は、労働者の搾取によってなりたつゆえに搾取なき経済社会――プロレタリアート独裁のための闘争を教示した。 この簡単な理論は、こんにち、すでに小学生でも知っている周知の常識となった。ところで、このマルクス・レーニン主義が社会の常識となったということは、逆にいえば、イデオロギーが、革命的魔力を失ったということなのである。 賃金労働者の解放、貧窮者の救済は、団結と闘争によるブルジョワ階級制度の打倒以外にはないということを、組織労働者はもちろん、被支配者のだれもが知りつくしているにかかわらず、それでも、彼らは賃金労働に生活をゆだねているのが現実である。これはどういうことなのであろうか。 結局労働者は、搾取されることを認容しながら労働しているのであり、労働組合は搾取を少しでも小さくしようとする消極的意味あいしか現実にはもっていないことになる。すなわち、労働の価値、いいかえれば、労働者の生きることの価値は、資本と労働の妥協と折衷のなかに存在する。そこでは、プロレタリア独裁という革命は遠のいたのであり、なによりも労働者はそれを知っているのであってそれゆえ、彼らは修正資本主義という餌を食う豚だ。 すくなくとも、ビートはそう思う。その証拠に、最近の左翼の細分裂と退潮、混乱は、豚にとって、マルクス・レーニン主義がもはや餌ではなくなったことを証明している。なによりも力――生命力が左翼のなかには欠けているのだ。翼を失った妖怪になんの魅力があろうか。ビートは、極端と生命力をもとめて放浪する。 したがって、一定の場所で、一定の労働を生活のためにするということは、いかに弁解しても、要するに搾取されることを望むにすぎない。大学教授から沖仲仕まで、彼らが一日を労働で生きるということは国家と資本の支配者を富ますだけのことだ。 こうして、ビートの哲学は結論にたっする。国家と国旗、職場と労働、学校と家庭、それらにきれいさっぱりおさらばを告げよう、手を切ったらふりむくな。乞食になって働くな。労働と生活を引き換えクーポン制にしているプロレタリアートが、真の自由と解放をうるためには他人のための労働をいっさいしないことだ。 一億総ルンペン――だれひとり働くものがいなくなれば、いかに狡猾な支配階級も搾取することは不可能だ。国家と資本は、利潤追求の手段を失って崩壊することは必至である。 ビート乞食にとって、革命とは、乞食倍増運動の展開のみである。プロレタリアートはビート乞食をまねるだけで、革命は目のまえに横たわるはずだ。支配階級の豪荘な邸宅の門前に、労働者の変身した乞食の大群が、「もらいもの」に大挙しておしよせる光景をえがくとするなら、革命というもののヴィジョンが樹立されるだろう。 それは「永久ストライキ革命」とでも呼ばれる。少年のころ、唱歌に「元寇」というのがあったが、その替え歌は、五百余万の乞食/ザルもって門に立つ/オッサン、銭おくれ/穴のあいた銭おくれ、というのである。かくて、この乞食の大群の襲撃によって、ブルジョワが顔色なくするまえに、マルクス・レーニン主義は、非戦闘的、非労働者的イデオロギーとして、色あせる。 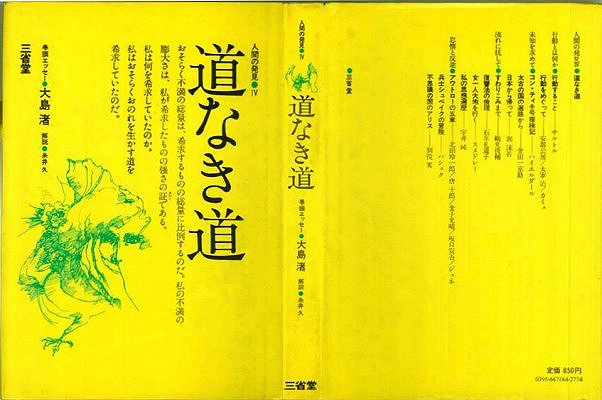 (ノーベル書房刊『乞食学(ビートロジー)入門』より) (ノーベル書房刊『乞食学(ビートロジー)入門』より)(『道なき道』人間の発見Ⅳ/160頁/ 「ビートになるか」/三省堂/1974年) ★写真をクリックで拡大→ 文化遺産としての除籍簿を残せ 相続登記には、戸籍、原戸籍、除籍簿の謄本が絶対に必要とされる。それがないと、被相続入(遺産を残した死亡者)の家族構成が分らず、相続人が誰かを証明できない。正規の婚姻から生れた子以外に、婚外の子がいるかもしれない。そのため、通常、男女ともども15歳ぐらいから子供をつくる能力があるとして、除籍謄本は被相続人のその年令までさかのぼって取る必要がある。 わが国の戸籍制度は、おそらく世界に比類のない正確さを誇るみごとなものである。その一族のルーツがすべて判明する。それだけに公開を制限して、プライバシーの保護がことのほか重要なことはいうまでもないが、それはともかくとして、除籍簿はまた、明治文明開化以来の近代日本史のドキュメントでもある。 次から次へと子供が生まれても死亡している古い戸籍をみると、平均年齢の低かった悲惨きわまる戦前日本の貧困がわかる。また、昭和18年月日不詳、ガナルカナル島に於て戦死と、極端なまでに圧縮された文字が語りかけてくるものには、一瞬、胸が迫る。 ところが、その除籍簿は戸籍法施行規則5条4項により、保存期間80年と定め、廃棄処分にするとある。明治・大正・昭和の何十億という日本人の生と死の激動の物語を秘蔵する、この民族の歴史的一大文化遺産を、わずか80年で葬りさることには、この国の文化政策の貧困に天を仰いで慨嘆せざるをえない。 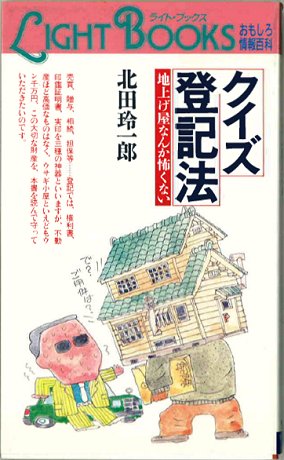 (『クイズ登記法』41頁/東京法経学院出版/1988年) ★写真をクリックで拡大→ |
||
|
|
||
| 前のページ/次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |
||
|
|