- p1 - 生ける法を限りなく民衆に近づけるために/井上孝次郎の西部魂/『回顧と展望』編集後記 『司法書士公論』創刊宣言 痛切な主張の拡声機に/『司法書士公論』創刊号編集後記 ◆ <p2> 私の空襲体験 ― くたばれ飛行機/乞食(ビート)になるか/文化遺産としての除籍簿を残せ <p3> 司法書士業余作家からの文学的メッセージ |
||
|
生ける法を限りなく民衆に近づけるために 本書に収録された司法書士実務のドキュメンタリー二四篇は、「法学セミナー」に、一九八八年一二月号から一九九〇年一一月号までの二年間連載されたものであるが、本書上梓の企意・目的について述べようとすれば、どうしても先行書である『司法書士の実務と理論』(江藤价泰編=一九九〇年一一月・日本評論社刊)にふれないわけにはいかない。 前掲書もまた本書と同様、「法学セミナー」に、一九八六年一一月号から二年間にわたって、「講座・司法書士の実務と理論」と題して連載され、いっぽう本書は、「講座・司法書士実務の現実と課題」と銘うたれたものであるけれども、両書ともどもその意図するところは、現場感覚に裏うちされた実務の理論的な問題提起、あるいは、司法書士の臨場実務から発想されるダイナミックな応用的法知識、また独自の実践的裁量、技術の高度かつ多彩な水準を披露し、発表するということにつきたと、いえる。 しかし、両書には明らかな差異がある。 『司法書士の実務と理論』が、司法書士の、司法書士による、司法書士のための現場実務のノウハウを、日常職務のリアルな経験をもとにして、すこしでも理論化・普遍化することに総力をあげて肉迫し、その成果を世に問うものであったという意味において、「理論篇」であるとすれば、ひるがえって本書『ドキュメント司法書士』は、ひたすら地雷原と戦車壕におののきながらの前進、前進、また前進をくりかえす「実践篇」である。 したがって、読者諸氏、ことに新進気鋭の司法書士、そして、この蠱惑にみちた一世紀有余の歴史をもつ極めて民族的な法職――法律実務家(香川政府委員答弁・第八四回国会衆議院法務委員会昭和五三年六月七日会議録二九号)への道を志そうとするヤンガー・ゼネレーションは、この姉妹篇的構成をとる二書を通読することによって、「司法書士入門」の計量器をパスしたといって、けっしていいすぎではない。 ・・・・・・ところで、本書の各執筆者は「関西司法書士実務研究会」のメンバーであり、すべて大阪司法書士会の所属である。運河と煤煙と排気ガスの街、大阪――貪婪な商魂、巨大な胃袋、原色の狼雑でなりたつこの西日本最大の都会は、大阪弁をあやつる、なりふりかまわぬ中小・零細商工業が蝟集する大いなる俗物の一大重層地帯である。 シカゴ・バラードのような日本最大の歓楽街をかかえ、不動産民事介入暴力にもこと欠かない。また、伝統的に、定住外国人の密集という民族的マイノリティの諸問題も避けて通ることはできない。それゆえ執筆者には、古参の老獪、中堅の自恃、新鋭の冒険というメンバー的編成を必要とした。こうしてメンバーは幾度かの会合のすえ、とにもかくにも現場(多様な事件)、現実(多層な依頼者)の発見と遭遇から出発した。 それは、現場、現実との司法書士の接舷が、どんな経緯をふんでおこなわれ、心理的紐帯がどうやって形成されていき、また現場、現実における民衆がわの法的要請が、司法書士の心象熔鉱炉のなかで、どのように灼熱し、やがて、いかなるどろどろした赤熱の銑鉄を吐きだしてくるかの生産工程的リアリズムのストーリイになることを約束した。 とはいえ、司法書士自身の体験、赤裸々な職務の実態を、はたしてそのまま記録日誌風に発表することが、社会的に有意義なことかどうかについては、いささかの疑念なしとしない。ケースによれば、国家のあまたの規制と、民衆の限りない利己的要求との利害の対立を、白日の下にさらけだす結果を招来することもありうる。 したがって、本書のドキュメンタリーが、ほとんどクソ・リアリズムに近い、泥臭い嘱託人との接遇、事件処理の推移、その結実をえがきだすことは、明治以来、伝統的職制として国家と民衆の中間に介在して生きてきた司法書士の職業的宿命からして、はなはだ困惑と苦渋にみちた告白になりかねなかった。 書店に氾濫する法理論の解説、研究の書を、いくらひもといてみても、この砲声とどろく最前線からの苦悩する肉声にこたえてくれるなんらの満足しうる解答もえられはしないのである。 さらに、このドキュメンタリーを連載していく過程において、司法書士には、前掲書『司法書士の実務と理論』で、編者の江藤价泰教授が、その序論「司法書士の基本的性格」に述べられたとおりの制約に、まさしく神経質にぶつからざるをえなかった。こんにち現在、実務の日常性のなかにおいてさえ、司法書士はけっして「第四の法曹」でもなければ「堂々たる司法書士」でもない。 司法書士が「国民の権利の保全に寄与する」――という法第一条に忠誠を誓おうとすればするほど、「司法書士制度の内奥、またその職務の実態まで踏み入ってみた場合、司法書士の基本的性格あるいはその職務が、法的ないし制度的に整備され、明確になっているとは、必ずしもいえない現実」に直面しないわけにはいかないのである。 たしかに、昭和二九年の法務事務次官回答による司法書士「代書タイプライター論」から始まって、昭和五二年の松山地裁判決、昭和五四年の高松高裁判決を通じ、「司法書士とはなにか?」は、ひっきりなしに問われつづけている。そして、「画期的ともいわれる五三年法改正にもかかわらず、残念なことに、司法書士は明確に法律家として性格規定されたわけでもない。五三年法改正は、制度発展のための基盤整備を実現」したにすぎないとすれば、この町の辻、街の角で、ひとびとの日々の法生活に立会う「法律上の助言者」「人民の友」は、いま現在の時空において、所詮、アウトサイダー的法職者の位置にしか浮遊することができないのであろうか? はたせるかな、日本弁護士連合会は、昭和六二年九月末、日弁連業務対策委員会の答申をうけて、『弁護士法との関連で問題となるべき司法書士の業務とこれへの対策』と題する意見書をまとめ、弁護士のみが絶対無二の在野法律家であるとする観点から、弁護士法七二条を、あたかも水戸黄門の印籠のように掲げて日本司法書士会連合会にたいし申入れをしてきた。 「弁護士が一般的普遍的な意味の法律専門職であるのに対して、司法書士は法に明記された極めて限定的な範囲でのみ法律業務を行い得るにすぎ(ない)」とし、「司法書士の中心的業務は、依頼者の代理人としてなしうる登記又は供託に関する手続と・・・・・・審査手続である。その手続の性質は、いずれも行政手続であり、司法手続ではない」――等と述べているが、しかし、「弁護士の社会的機能の実態は、弁護士の法律事務の独占どころか、古典的職務である訴訟代理についても、簡裁事件や地裁乙号支部事件をみるかぎりにおいては、地域住民の裁判を受ける権利の保障を、もはや、弁護士に期待するのが無理だという状況が生じている」といえるのである(田代季男「終講・司法書士制度の展望」『司法書士の実務と理論』)。 明治五年(一八七二)、江藤新平初代司法卿が『司法職務定制』を制定し、人民の権利擁護のために三職(証書人・代書人・代言人)を創設して以来、大正八年(一九一九)の『司法代書人法』(法律四八号)、昭和一〇年(一九三五)の『司法書士法』(法律三六号)、昭和二五年(一九五〇)の『司法書士法』(法律一九七号)等々の制定を通じて、弱者をかえりみないで絶対唯一のエリートを揚言する法律事務独占(『法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律』〔昭和八年法律五四号〕、弁護士法七二条)者の通過した荒廃した道路を、ひたすら低廉な報酬で黙々と修復してきたのは、司法書士ではなかったか。 路傍にうちすてられた「無告の民」の、人間としての、法の保護を受ける権利を底辺でにない、援助、保障してきたのは、この列島の寒風熱暑の離島にまで割拠して、百十余年の歴史を生きつづけてきた司法書士であると位置づけたうえで、ふと私は宮沢賢治の有名な詩「雨ニモマケズ風ニモマケズ」を想いおこさないわけにはいかなかった。 本書は、ひっきょう、この宮沢賢治の詩精神の延長線上に立つものにほかならず、それゆえ、私たちの告白的実務ドキュメンタリーは、ノルウェーの画家ムンクの絵画のように民衆の内奥の熱い叫びの代理人としてのそれである。なお、本書のドキュメンタリーに登場する人物は、すべて仮名であることをおことわりしておく。 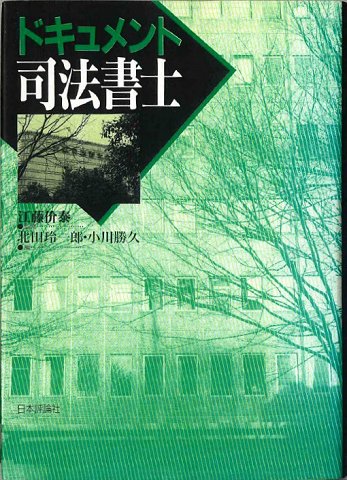 一九九一年五月 北田玲一郎 (『ドキュメント司法書士』はしがき/日本評論社/1991年) ★写真をクリックで拡大→ 井上孝次郎の西部魂 北田玲一郎 司法書士の屈辱的な身分復権闘争を一管の筆に託し、戦前特高の弾圧にもめげず叫びつづけた幾星霜 1 井上孝次郎が、司法書士の前身である司法代書人を大阪市東区谷町で開業したのが、大正11年。府県令によって定められていた「代書人規則」から脱皮した「司法代書人法」が、法律第48号をもって創定されたのが、その3年前の大正8年4月9日のことであった。 それゆえ、彼の半生は、司法代書人から司法書士に改称される歴史の歩みであったとともに、また、その司法補助機関としての職業の重要性にもかかわらず、歴史的に不当に蔑視され卑しめられてきた社会的待遇にたいする闘争の年月であったといえるのである。 当時の業界の急進的ヌーベル・バーグ(新しい波)であった少壮気鋭の彼は、裁判所構成法の一部に属する枢要な日常の職責をにないながら、依然としていちぢるしい身分上の冷遇侮蔑の朝野法曹界の評価にはげしい憤りを燃やし、同時に、どうにも手のつけようのない業界の古い牢固とした伝統的因習と、ぬきがたく無自覚な同業者の存在をみて苦悩しつづけるのである。青春の抗議であった。 しかし、それは、なにも井上孝次郎のみの憤りと苦しみに帰せられるべき性質のものではなく、おもえば、司法書士制度そのものが宿命づけられてきたひとつの必然的状況にほかならなかったのだ。 すなわち、明治5年の太政官布達で布告された「司法職務定制」と、翌明治6年に布告された「訴答文例」によって、訴状等の作成については、代書人が書いたものでなければ証拠力がないというきわめて重要な権限を有し、なくてはならない公的機関として尊重されていたにかかわらず、発生当初同列にあった代言人は明治9年の代言人規則を経て明治26年法律第7号をもって弁護士法の公布をみ、証書人は明治19年の公証人規則を経て、明治41年、法律第53号公証人法の公布となり――もっとも、そこには、政治権力の支配的趨勢があったとはいえ、代書人のみが代々の先輩の無自覚なふがいなさのため、自らもとめて社会の落伍者への道をあゆんできたのであった。 要するに、それは、同業者のすくいがたい安逸と怠惰がうんだ弁証法的帰結として、多言を要しないであろう。ところで、青年井上孝次郎が、司法代書人を男子一生の仕事としてえらび、開業したのは、ときあたかも、このとりのこされてきた業界が、ようやく大正8年にいたり司法代書人法の制定をみて、不本意ながら陽の目をみた直後であり、新鋭司法代書人たちのあいだに澎湃として復権への意欲がみなぎりはじめたときであった。 当然、彼らにとって、当時の現行司法代書人法は、制度的に不徹底きわまるものであり、そして、屈辱的、隷属的であって、憤懣やるかたないものにほかならなかった。こうして、彼は、その蓄積する不満を、ついに該法の根本的改正の提唱にいちずに凝結させ、一方で当時の盟友たちの司法代書人関西聯合の改正案をいまだぬるま湯的なものとして批判しながら、痛烈な熱血の論陣を『法律新聞』(第2762号、昭和2・11・25)にはるのである。 ときに、紀元2587年であり、その『司法代書人及司法代書人法の改正を論ず=司法大臣に対する希望』は、同紙編集部の「法界革新」というトップ見出しつきで、本号の冒頭をかざった。 2 つぎにそのあらましを紹介しよう。ここで、井上は『文書人』と改称することを提案している。その理由としては、「それ古きを捨て新しきを求むるは世の常なり――中略――『代書人』なる名称はあまりに古きに過ぎ現在の司法代書人の職務に適合せず而して其文字は所謂『モノカキ』を連想し――中略――現今の司法代書人は往昔の代書人の如く単に紙に字を書くに非ず前述の如き事務を処理する技能を要し其労力と智能とは同日の比に非ず」とのべる。 ひるがえって、こんにち、わが業界において、現行の『司法書士』の名称は、依然として旧態の代書業を意味し、象徴するものとして、識者の顰蹙を買っているが、おもうに、まさにその点においても、井上はおそるべき洞察力をもったえがたい先覚者であったわけである。 「二、一定の資格条件を定め認可制度を改め登録制とするについて」 ここでは「司法代書人の制度は現代に於て必要欠くべからずして――中略――人材を求めんとするには適当なる試験(判任官程度)の合格者にして人格の士を以て資格条件とし――中略――現在司法代書人の資格は認可せられたる所属地方裁判所の管轄外に出てすら其地に於いて再び認可を得ざるべからず如斯は不便なるは勿論法律上の統一の効果を疑うべく吾人の人格権も甚だ小範囲に限定せらるる事となり――中略――帰結として現行の認可制を改め一定資格条件の下に登録制度となし」と主張する。 この主張と昭和44年1月20日発行の『日司連だより』(第61号)の第1頁に掲載された日司連会長、沢口祐三の『国民の期待にこたえつつ堂々の主張を』中の「――過年度の法改正成立に際し併せて可決された附帯決議『会員の自主的研修と懲戒制度の自主的措置の促進』『国家試験制度の検討』の2項目は、重要課題として準備体制に入るべき問題と考えます……」を読みくらべるとき、卒直にいって、読者はどのような感慨にとらえられるであろうか。とはいえ、井上と沢口は同一人物なのではけっしてないのである。 「三、司法代書人の受くる報酬について」 ここでは、「司法代書人は地方裁判所長の定めたる書記料を受くることを規定したり――中略――而して現在の一枚単位を以て律するは因習を辿るものにして往昔の遺物ともいうべく旧套を脱し現在の職務に適合する所の統一的報酬を規定するか司法代書人会に其権限を与え適宜之を定め監督官の認可を受くる制度と為すを以て改正の要点とす」と力説する。 かんがえてみるのに、この昭和2年――満州事変4年前の井上の主張は、太平洋戦争後20数年を経過した昭和44年の現時点において、いったい、どれだけ進歩したであろうかとおもうとき、暗然たるおもいなしにはいられないのは、ひとり筆者だけであろうか? かのラマルクやダーウィンの進化論は、ここではたんなる戯言にすぎず、半世紀のあいだ、司法書士の時計は、まるでスペインのあの有名な超現実主義(シュル・レアリズム)の画家=サルバドル・ダリのタブロー『記憶の固執(柔らかい時計)』のなかの溶解した時計のように、ただひとつの時間しかしめしていないのだ。 井上の『司法代書人及司法代書人法の改正を論ず』の要点は、ほぼ、以上の三点にしぼられるが、本論稿の前段では「登記と司法代書人の職務」「司法代書人法成立の概略と現状について」「明治初年に於ける司法代書人の制度(布告第二四七号)について」と題して「大阪に代書人ができて以来の代書人沿革史ともいうべきものを編纂すべく、代書人に関してのあらゆる文献を、永年苦心調査し、蒐集保存し、古新聞、古雑誌の一頁といえども、宝物のごとく秘蔵している」(「大阪法曹経済新聞」第473号、昭和13・3・25)と紹介された文献約薀蓄をかたむけて論述するのである。 3 井上孝次郎は今日健在である。それどころか、現在、第一線司法書士として大阪府吹田市の事務所で寧日ないありさまだ。去る3月筆者は「大阪司法書士会会史」編纂委員として、委員長である彼を訪問、歓談の機会をえたが、なるほど噂のとおり、彼が半生にわたって蒐集した古文書の類いは、おびただしく彼の書斎にひしめき、ぶきみに息を殺していた。そして、彼は、「私は自叙伝を――ええ、私の自叙伝をかくつもりです」と、老いの眼を輝かせ、くりかえしかたった。彼がにぎりしめるペン先には、なお衰えることのない闘志、いいかえれば、あの戦前の特高に思想要注意としてマークされてもひるまなかった論客魂が鬼火のように燃えつづけていた。 そのあと、彼が、じっさい宝物のように蒐集物の堆積の山のなかからひきずりだしてきたものは、昭和5年4月の第1号から昭和9年1月の第10号にいたる「司法代書人会大阪支会」の機関誌ともいうべき会報の綴りであり、毎号執筆したその健筆の軌跡であった。彼はそれを筆者につきつけ、読めとせまった。一読して、それはダイナミックな迫力にみち、格調ある戦前調文体には、彼の青春のやみがたい血潮が脈うちながれていた――。 そして、筆者がかんじたことは、なによりも、その井上のいだいた業界改革の精神――あのアメリカの若者たちが、西部の曠野の開拓をめざして幌馬車をつらねて進んでいったフロンティア・スピリット、あの西部魂は、こんにちの大阪司法書士会の会員の群のなかに、なお連綿として生きつづけているという確信にほかならなかった。 姑息逡巡する東部――東京にたいして、進歩的で革新的なのはつねにこの大いなる西部――大阪ではなかったか。井上孝次郎の一管の筆に託したパッションは、けっして滅びはしないのである。 (『司法書士公論』創刊号40頁/昭和44年6月1日) 『回顧と展望』編集後記 一国の興亡は文化にある。組織、集団の興亡も、けだし、その文化の軽重に命運がかかっているといわねばならない。その意味で、本誌発刊を企図した大阪司法書士会、多額の費用を投じて惜しむことのなかった記念式典実行委員会に、ふかく敬意を表するものである。 いま、時代の潮流は大きな転換期にさしかかっている。人間と文明の未来は予測不可能な危機的暴風雨をむかえようとしているかにみえる。こうした時代に、巷の法律家群といわれる司法書士制度の存在理由にも内外をとわず、いっせいにするどい問いなおしがはじめられている。われわれもまた、この激しい査問の嵐のなかへ一度は船出していかざるをえないのではなかろうか。 こういうときに、制度制定が50周年に当面したわれわれの過去と未来を凝視し照射する本誌が発行されたことには、大いなる意義をみとめざるをえまい。古老がふみしめてきた長い歴史の血と汗、新進がゆめみる明日の業界の誇りたかき楼閣を、できるかぎり誌面に充溢させるべく、編集能力のすべてをそこに投入した。それらは、すべて司法書士とはなにか?という内外の問いへの本質的なこたえを準備しているだろう。 それにしても本誌の編集には心身を摩耗した。もはや多くをかたりたくはないが、ただひとつかいておきたいことは、きらに50年後に本誌がどのような遺産としての重さをもちうるかということが、疲労しきった私の神経質な気がかりにほかならない。 最後に執筆いただいた各位に感謝し、協力ねがった副委員長中川隆逸、雪本源、中川享の各氏の名をとどめる。ことに中川隆逸氏には物心両面のご苦労をかけた。それと、レイアウターの白石星児氏には、東京・大阪往復5たび、いたくお世話になった。しるして、ふかく謝す。 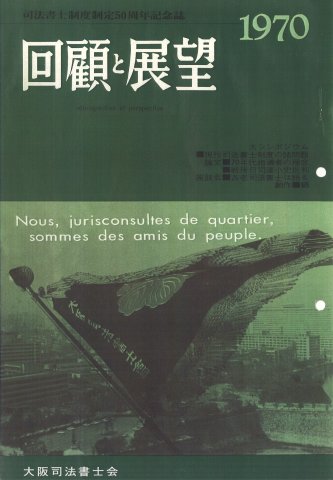 (1970・11・11=北田) (1970・11・11=北田)(『回顧と展望』) ★写真をクリックで拡大→ 『司法書士公論』創刊宣言 痛切な主張の拡声機に おもえば、一九六四年の「臨時行政調査会」の答申による「司法書士制度廃止論」は、われわれの百年の太平の夢をやぶる衝撃的な黒船来航にひとしかった。全国津々浦々に警鐘は乱打され、われわれは一大反対闘争を組織して、この危機をのりこえたのである。 ひきつづき、一九六七年の「司法書士法改正」が意味するものは、一言でいって、司法書士制度の文明開花であったと認識すべき性質のものではなかったか。いまや、われわは歴史的に、現代司法制度、行政制度のなかに、近代的自我を確立するためのはげしい揺籃期を体験しつつあるといっても過言ではないのだ。 たしかに現在、内的にも外的にも、わが業界にはひとつの大きな激動が押しよせようとしている。国家試験制度への改善、真の法律家的使命の確立、内部変革のための青年司法書士の育成、会指導者層の責任自覚、機械化の進行による登記事務の産業革命……等々、ことごとくが重大な試練をはらんでいるのである。しかし、われわれの存在理由(レーゾン・デートル)はただひとつ――司法書士は他の法曹分野の高踏性にひきくらべ、つねに即民衆的に、大衆の権利保全のための確実・濃密な対話者として、法曹界の広大な下部構造を黙々とささえてきたという自負であろう。 雨の日も風の日も「町の小さな法律屋」として、汎大衆の信頼と期待にこたえてきたという一事こそ、われわれの絶対的矜持にほかならない。この立場から本誌は発刊される。われわれはここに依拠することで、真に社会にとって不可欠な一重要職業人がわが国知識階級の一環として、その力強い発言によって、政治・経済・法律・文化の担い手であることを明示するつもりである。 実際、われわれはまるでマゾヒストのようにながいあいだ沈黙してきたが、もう黙っているわけにはまいらぬ。本誌はその痛切な主張の拡声器たらんと欲する。われわれにも歴史への参加の季節がやってきたのだ。 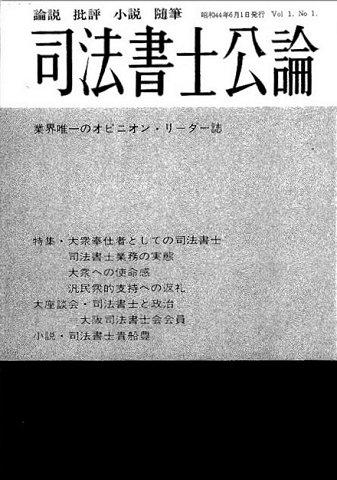 昭和44年(1969年)6月1日 『司法書士公論』創刊号編集後記 約半年にわたる準備期間中に、本誌の基本的姿勢について真剣な討議が重ねられた。どうしてもここにかいておかねばならないことは、本誌の真に自由な立場についてである。われわれはいかなる司法書士の公的組織にも所属していないし、また後援をえているわけでもない。完璧に自由な独立体であり、その遊撃的機能のみにいっさいを賭けている。それゆえ発言は固有の責任においてなされたものである。 私は現在の法務行政と司法書士との関係はつまるところ、ソ連とチェコの関係にはなはだ相似しているとの判断をもっている。一見自由があるようにみえても、それは支配権力によっていつ蹂躙されるかわからないかりそめの自由である。 もっとも現代はたんに司法書士のみならず、階級闘争はどうやら終りをつげ、権力と大衆、大国と小国、法秩序と反既成が世界的規模で、世紀末の混沌のなかへ漂流をはじめているかにみえる。未来はだれにもみえないのだ。とはいえ、われわれの職業にかえっていえば、支配と被支配、統制と隷属のこの悪しき関係からの脱却は急務であり、悲願である。そして、これこそが本誌創刊の本質的課題と使命にほかならない。 この職業的主体性の確立という座標軸から本号の特集と座談会は企画された。そのほか数多いエッセイのなかにも、そういうコケの一念が一貫してながれているはずである。 業界論客史は連載していきたい。えがたい一匹狼たちを全国的な規模でほりおこし、その激情に評価をあたえていきたい。あの戦前の暗かった官尊民卑と弾圧の時代の論客にはもう一度その怨念にライトを浴びせる必要があると痛感するのは、はたして私だけであろうか? 創刊宣言でものべたように、われわれは本誌の機能をフルに発揮して、永い間沈黙を余儀なくされてきた司法書士の文芸復興(ルネッサンス)たらんことを執拗に希求している。こんごはたんに業界のみの問題にとどまらず、法、税、住宅、公害、交通、犯罪等の社会事象にも、職業的に鍛錬された眼からのメスをいれていきたいし、その道の専門家との対談なども用意している。 ともあれ、われわれは後にも先にも司法書士以外のなにものでもない。この職業をこよなく愛し、この職業によって社会と連帯するのだ。そして、いうまでもなく自由人であることを希う。 くりかえすが、われわれは真に自由な立場でこの雑誌をはじめた。それゆえ、たよるのは、読者の共鳴とあたたかい支援のみである。一抹の不安と謙虚な戦慄をおぼえつつ、ここに創刊号を世におくりだす。(北田) 昭和44年(1969年)6月1日 |
||
|
|
||
| 次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |
||
|
|